中学生・高校生になると勉強時間は、どうしても増えていきます。
勉強がまずまず楽しいという人は問題ありませんが、勉強することが苦痛・大変という場合、音楽を聴きながら勉強をするのもいいのでは?と思うものです。
もちろん、私も音楽を聴きながら勉強をしたり、仕事をしたことがありますが、
その理由は、いくつかの研究を見ても分かりますが、人間本来の能力を考えてみても分かります。なぜ、音楽を聴きながら勉強をすることをオススメしないのか、解説します。

音楽を聴きながら勉強をしたら、時間が早く過ぎた感覚があったのに…。
それって集中できていたってことにならないの?
音楽を聴きながら勉強をすると集中できるのか?

音楽を聴きながら勉強をすると、時間が経つのが早く感じられたという経験をしたことがあると思います。
これは、何かに集中していたからではなく、刺激が与えられて脳内からドーパミンが放出され、快楽を感じているのです。
もちろん、心地よさを感じながら勉強をすることが悪いとはいいませんが、問題点は、
という点です。
つまり、勉強中に音楽を聴くことを繰り返していくうちに、次第により強い刺激(音量が大きくなる・BGM的ではない音楽など)の音楽に変わっていく可能性があるということです。
脳内の知っておきたい基本的なことは、根気強くなるには意思や訓練が重要?脳内の仕組みを解説の記事を参考にしてください。
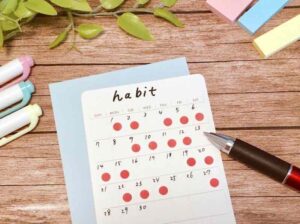
なぜ人間には耳がついているのか?【音楽が目的?】

人間に限らず、多くの動物には耳がついています。
なぜ、多くの動物に耳がついているのかというと、
というのが原点です。そんなこと分かっている!と言われそうですが、これはとても重要な視点となります。
現代の私たちは、日頃命を危険を感じることはなくなりましたが、古代はどうだったでしょう。

狩猟をしている時に、獲物の動きを注意深く見る必要があります。
だからと言って、獲物に全神経を集中させる訳にはいきません。
背後から、動物が襲ってくるかもしれないし、別の村の人が襲ってくるかもしれません。
だから、何らかの音が聞こえた時に、その音は、危険なサインなのか、気にする必要がないのか、私たちは瞬時に判断をし、命をつないできました。
別の言い方をすれば、音を聴きながら、獲物をとることに完全集中できないからこそ、命を守ることができたのです。
つまり、
ということです。
そのために、次の様な簡単なことでも、能力は下がることが実験で確認されています。
【実験結果】非常に簡単な作業でも音楽を流すと作業効率は下がる

東北大学で、次のような実験が行われました。
シンプルな実験で、テスト音が聞こえたらボタンを押すというものでしたが、次の様な条件付きでした。
| CaseA | ヘッドホンの片方から雑音を流し、もう一方からはテスト音を流す。 |
| CaseB | ヘッドホンの片方からジャズピアノ音楽を流し、もう一方からはテスト音を流す。 |
結果は、CaseBの場合、音量の大きさに関係なく、ボタンを押すまでの時間に遅れが出たというものです。
つまり、日常的に存在する音を私たちは気にせず聞き流すことができますが、音楽になると注意がそれてしまい、「ボタンを押す」という非常に簡単な行為でも遅れてしまうということです。
先に触れた「命を守ること」とも関連していることが分かります。
これは、大学での実験ですが、あなたが仕事をしている時はどうでしょうか。
この機会に振り返ってみてほしいと思います。

でも、物凄い静かな図書館って落ち着かない気がするけど、どうなの?
防音室のように、全く音が無い空間では集中できるのか?

自然ではない音(音楽を含む)があると、簡単な作業であっても遅れが生じることが分かりましたが、防音室の様に無音空間だとどうでしょうか。
これも人類の歴史を考えてみるとおのずと答えが分かります。
この事も科学的にすでに証明されています。
理由は、人類史上のほとんどの期間、無音状態はなかったためです。
- 風に吹かれて葉がザワザワとする音
- 水が流れる音・波の音
- 小鳥の鳴き声
- 人と人との会話 など…
命の危険とは程遠い様々な音に囲まれて私達は暮らしてきたために、その程度の音がある環境が最も集中できるのです。
防音室の様に完全に音をシャットアウトした空間が作れるようになったのは、人類史の視点から見れば、極最近のことです。
つまり、何も音がしない状態は、不自然であるということです。
日本を代表する様々な文豪の方々が、田舎町の宿に行き作品を書いたのも、自然の適度な音に包まれる感覚が心地良かったのかもしれません。
自然であることの面白さは、兄弟喧嘩にうんざり?これを知れば兄弟の子育てが楽しめるの記事でも感じられるはずです。

まとめ【音楽の存在が良い場合もある】

冒頭で触れた様に、「音楽を聴きながら勉強をする」ということの効率について紹介しました。
中高生くらいの学習で、しっかりと理解をしないといけない様なものを学ぶ時には、自然に近い状態が最も効率的です。
実は、音楽に限らず、室内空間の装飾によっても、人の集中力は変化します。
ですから、もし少しでも効率良く勉強をしようと思うのであれば、
- できるだけ自然に近い環境で勉強をする。
- 大声ではない(何を言っているか分からないくらい)の会話がある環境で勉強する。
- 音楽・ラジオ音声など人工的な音はカットした環境で勉強をする。
ということが重要です。
だからと言って、音楽の存在が悪という訳ではありません。
リラックスしたい時に音楽の存在はとてもありがたいものです。また、単純な作業をする時に、作業効率は落ちてしまいますが、楽しい音楽が流れていることで、持続させやすくもなります。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
人間って意外と繊細なところもあるものだと思います。だからこそ、何万年と命を繋いでくることができたのではないでしょうか。
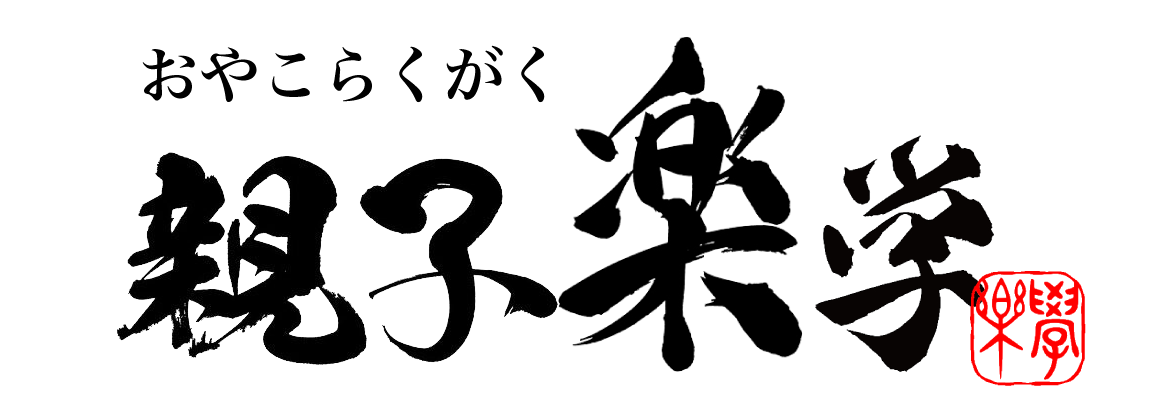
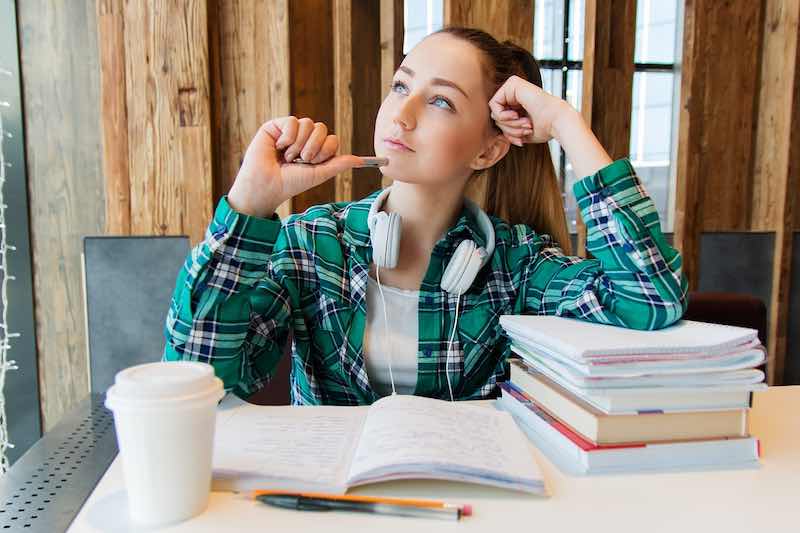








コメント